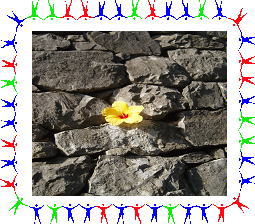
はるか昔、20代半ばのころ、何も考えずにひたすら
リゾート気分で行ってしまった1回目の旅。ところが、
夜、未だに恐ろしい悪夢にうなされて一睡もできなかったため、訳もわからず、いや、わかろうともせずに、沖縄に対して漠然とした恐怖感を抱く結果となっしまいました。こんな情けない若者だったわたしが今回の旅に参加させていただける日が来ようとは夢にも思いませんでした。ですので、私ごとの話が長くなりますがもう少し続けさせていただきます。
30になってから日本語を外国の人に教えるという仕事に就くようになりました。これも、やり甲斐があり、一生できそうな職業?と安易な考えで始めてしまったため、程なくことばの持つ背景や歴史を知らずに道具として教えることの理不尽さ、アジアの学習者の方々と触れ合うときの自分の身の置き所というものに戸惑いを覚え、好きな仕事なのに続けるのが辛いという微妙な心境になってきました。
心の迷いを吹っ切ろうと40代になってから進学した大学院。研究には無縁の人生を歩んできた人間には非常に無謀な決断でしたが、人としては多くのことを学び、物事を深く考えるいい機会を得ました。大学院で何人かの尊敬できる方々に出会えたことも幸運でした。そのお一人が今回の旅に琉球大学の学生さんたちや日本語ゆんたくサロンという日本語のボランティアグループの方々を連れて参加してくださった與那覇麻孔さんです。彼女のお招きでゼミ仲間と一緒という気丈さに加勢されて沖縄を訪問したのが、2回目。このときから、沖縄に対するわたしの想いは、漠然と怖ろしげな場所から、一気に何度でも訪れたい、癒しの場所へと劇的な変化を遂げました。もちろんそれは、リゾート地としての癒しではありません。沖縄の文化に触れ、沖縄の人達の温かい心と複雑に交錯する日本という国家への感情、それらを文献からではなく直接お会いして感じ取ること、沖縄戦の戦跡を訪れ、鎮魂の祈りと共に今の自分たちにできることは何かと想いを馳せるゆったりとした時の流れ、そういった全てのものが、過去の無知ゆえの恐怖心をゆっくりと氷塊してくれたのだと思います。
そして、2006年は運良く2度も沖縄を訪問する機会を得ました。1度目は日本語教育関係のイベントに参加。そして2度目、通算4度目の沖縄旅行が今回の川崎のハルモニと行く沖縄の旅でした。もちろん、この旅行が沖縄旅行の中だけでなく、2006年度のわたしにとってのハイライトとなる旅となりました。
一昨年から桜本のふれあい館へウリハッキョの共同学習者として伺うようになり、わたしの人生観はかなり変わってきていました。仕事に行き詰まってストレスがたまり気味なときも、ハルモニ方とたわいないお話しをしたり、時に生半可なわたしの人生では想像も付かないような一世のハルモニ方の人生の一頁のお話をお聞きすることで、自分のストレスなど、取るに足らないものであることに気づかせていただきました。ハルモニ方の生き様は本当にいい意味で逞しくて眩しいです。そして、数々のかん難を越えてこられたからこそ、今を懸命に楽しんで生きておられるのがわかります。ハルモニ方から見れば일번 사람であるわたし、それは「うちなーんちゅ」から見た「やまとぅんちゅ」であるわたし、と通じるものがあります。そして、それは外国にルーツを持つ人々と日本に住む日本人であるわたし、とも重なってくるのです。
沖縄読谷村のおばあと川崎市桜本のハルモニ…どちらもその生涯を日本という国民国家のせいで語りえぬほどの苦労を背負われて生きてこられました。その方々が共に想いを語り合ったことは本当に貴重な機会だったと思います。それは、「ゆんたんざ沖縄」と「花はんめ」という2本のすばらしいドキュメンタリー映画の出演者同士の交歓会でもありました。そのような場に、このような自分が身を置かせていただけたことは本当に光栄なことでした。まるで美味しいところだけつまみ喰いをした子どもような後ろめたさはありましたが、そのすばらしい場に立ち会えたことへの興奮と感謝の念が何倍も勝りました。
不思議に思ったこと、それは知花昌一さんとそのご親族や友人の方々との交流会のときのことです。職業に似合わず、私は人見知りをするたちで初対面の方にはなかなか打ち解けて話しかけることができません。ところが、今回はそばにハルモニたちがいてくださったからでしょうか、知花さんや沖縄のおばあたちにはお目に掛かったときから、わたしは前からのお知り合いのようにどんどん話しかけることができたのです。お隣に座った知花さんのおばさまにあたる方はチビチリガマで生き残られた方でした。座ったとたんに、親しく話しかけてくださっていろいろと会話が弾みました。気さくな明るい方だなぁ、と思っていたところ、話が佳境に入ると、ふと「わたしらは本当はつらいから何も話したくないですよ。ずっと話せなかった。人に話せるような話じゃない…」とおっしゃり、目頭を押さえられました。何ともことばの返しようがない一瞬…。人間の尊厳を問われるような試練などくぐったことのない者には共感できるはずもなく、ただオロオロとしばし見守りたい気持ちでした。しかし、その日のわたしは共に聞いてその辛さを共感し合えるお立場のハルモニ方の存在を身近に心強く感じながら、思わず「ありがとうございます。話そうというそのお気持ちだけでも本当に感謝しています。」と申しました。それを聞いてどう思われたかは不明ですが、わたしの手をとって握ってくださり、それから話を続けてくださいました。沖縄舞踊のステップもお見事で桜本のハルモニ方と同じぐらいパワフルな読谷村のおばあでした。そして、その席には黄徳子さんのアリランやトラジの歌が朗々と響き、賑やかな朝鮮舞踊やら華やかなフラダンスなど、本当に魅力的な人生の先輩方が繰広げるパフォーマンスが続出で、すっかり気持ちよく酔っ払ったわたしは、年をとるのが楽しみになった一日でした。
最後に同室のハルモニ方、バスの中で一緒に座ってくださったハルモニ方、そして一緒に旅行してくださったふれあい館の職員やふれあい館にゆかりの皆様、沖縄の皆々様、いくら感謝しても2006年度だけの感謝では絶対に足り得ない、本当にいい旅でした。どのシーンを思い出しても、宝物のようで思い出話がいくらでも書けそうなので、このへんで終わります。
最後に今回の旅の感想を一言で言うとすうならば、気恥ずかしいけどまさにこんな感じです。